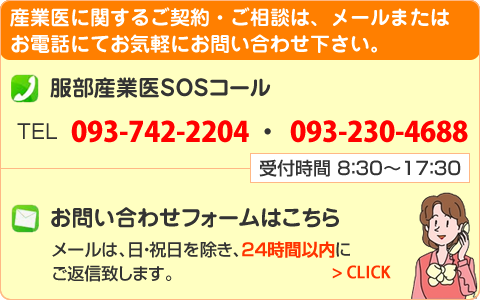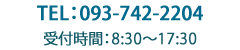ハンディーファンの使い方注意
- 2024年07月23日
- 未分類
こんにちは。保健師の宮本です。
ハンディファンの利用が浸透していますが、炎天下の屋外で使うとあたっている風が熱風になり逆効果になることがあります。
熱風にあたることで、体が暖まり熱中症の引き金になってしまうこともあるようです。
対策として、屋外で使う場合はハンディファンの風を熱風にさせないために、濡れタオルやミストで体を少し濡れた状態にし、水の気化熱による冷却効果を促進させるといいそうです。
ベビーカーに取り付けているのもよく見かけますが、風が熱くなってないかチェックが必要です。